「祈り」は信心深い人とそうでない人とで異なる影響を与えるという研究結果
最新の研究結果によると、信心深い人はそうでない人よりも不正行為を働きがちな傾向にあることが明らかになりました。また、この「信心深い人による他人をだます行為」は、祈りを重ねることで減少する可能性があるものの、逆に信心深くない人の場合は祈りを行うことで不正行為を行う回数が増加しがちな傾向にあることが明らかになっています。
The divergent effects of prayer on cheating: Religion, Brain & Behavior: Vol 0, No 0
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2153599X.2019.1574881
The divergent effects of prayer on cheating: Religion, Brain & Behavior: Vol 0, No 0
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2153599X.2019.1574881
Prayer makes non-believers more likely to cheat, study finds
https://www.psypost.org/2019/06/prayer-makes-non-believers-more-likely-to-cheat-study-finds-53843
宗教・脳・行動に関する最新の研究を行ったのは、ビクトリア・アローニャ氏率いるオタゴ大学の研究チームです。研究チームは信心深いアメリカ人153人と、信心深くないアメリカ人98人を対象に、オンライン上でスワヒリ語の翻訳タスクを行ってもらうという調査を行いました。被験者たちは自身の直感だけで17のスワヒリ語の意味を推測するように依頼されるわけですが、オンライン上で翻訳タスクを行うため、「単語を調べる」というチート行為を行うことが可能です。そして、被験者に対しては参加者の中で高得点を出した人には100ドル(約1万円)の報酬が渡されることが伝えられました。
このタスクを終わる前に、被験者の半数には祈りを書くように依頼します。被験者に対しては「研究によると、祈りを書くことはたとえあなたが神を信じていなくても、直感的な作業のパフォーマンスを改善することが示唆されている」と伝え、祈りを模写することが重要な作業であることを強調します。
https://www.psypost.org/2019/06/prayer-makes-non-believers-more-likely-to-cheat-study-finds-53843
宗教・脳・行動に関する最新の研究を行ったのは、ビクトリア・アローニャ氏率いるオタゴ大学の研究チームです。研究チームは信心深いアメリカ人153人と、信心深くないアメリカ人98人を対象に、オンライン上でスワヒリ語の翻訳タスクを行ってもらうという調査を行いました。被験者たちは自身の直感だけで17のスワヒリ語の意味を推測するように依頼されるわけですが、オンライン上で翻訳タスクを行うため、「単語を調べる」というチート行為を行うことが可能です。そして、被験者に対しては参加者の中で高得点を出した人には100ドル(約1万円)の報酬が渡されることが伝えられました。
このタスクを終わる前に、被験者の半数には祈りを書くように依頼します。被験者に対しては「研究によると、祈りを書くことはたとえあなたが神を信じていなくても、直感的な作業のパフォーマンスを改善することが示唆されている」と伝え、祈りを模写することが重要な作業であることを強調します。
テスト結果を分析したところ、信心深い被験者は信心深くない人よりも多くカンニングする傾向にあることが明らかになりました。ただし、祈りを模写してもらうと、信心深い人々の間で不正行為を行う回数は減少することも判明しています。一方で、信心深くない被験者の場合、祈りを模写してもらうと不正行為を働く回数が増加したそうです。
調査を主導したアローニャ氏は、PsyPostに対して「もちろんより多くの条件による研究を続ける必要がありますが、我々の研究結果は、神に祈りをささげることは信心深い人とそうでない人の間では道徳的な行動に対して異なる意味を持つものである可能性を示唆しています」と語り、信心深い人とそうでない人の間でみられた「祈りの模写」の効果の違いを強調しています。違いが生まれた理由についてアローニャ氏は、「これは信心深い人とそうでない人では、神の支配に対する概念的な違いが存在するからかもしれない」と説明しています。
調査を主導したアローニャ氏は、PsyPostに対して「もちろんより多くの条件による研究を続ける必要がありますが、我々の研究結果は、神に祈りをささげることは信心深い人とそうでない人の間では道徳的な行動に対して異なる意味を持つものである可能性を示唆しています」と語り、信心深い人とそうでない人の間でみられた「祈りの模写」の効果の違いを強調しています。違いが生まれた理由についてアローニャ氏は、「これは信心深い人とそうでない人では、神の支配に対する概念的な違いが存在するからかもしれない」と説明しています。

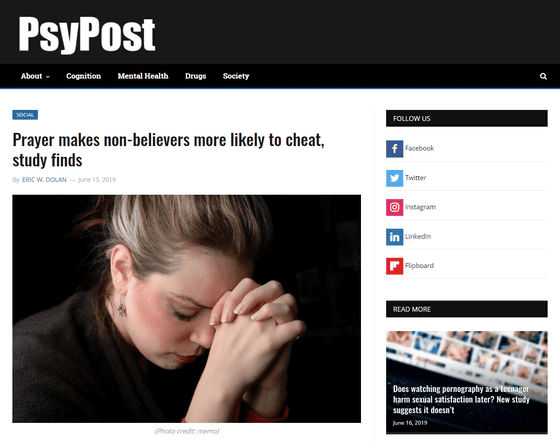
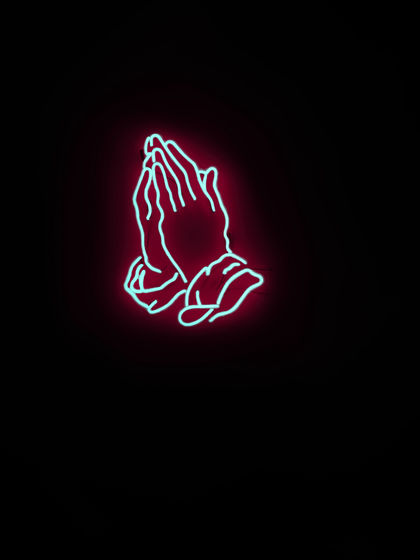

0 件のコメント:
コメントを投稿